こんにちは、しのらぼと申します
料理は科学 営業は心理学
をコンセプトに美味しさの理由を
科学と心理学を駆使して研究しています
飲食は再現性のあるビジネスである
という理念から組織の拡大、人材育成についても
研究しています。
当ブログ、X(旧Twitter)、インスタグラムで
研究の成果をを発信しています。
ぜひご覧ください。
さて、今回は
新入社員が辞めないように
教育することは正しいのか?
というテーマで記事を書いていきます。
この記事はこんな方におすすめ
・新人スタッフを採用した
・新人スタッフの教育担当になった
・新人との接し方がわからない
この記事を読むと、
・新人の育て方がわかる
・新人との接し方がわかる
・仕事のストレスが軽減する
私の答え
当記事のテーマである、
「新人を辞めないように教育するべきか」
という問いに対して、
私の個人的な考えは「NO」です。
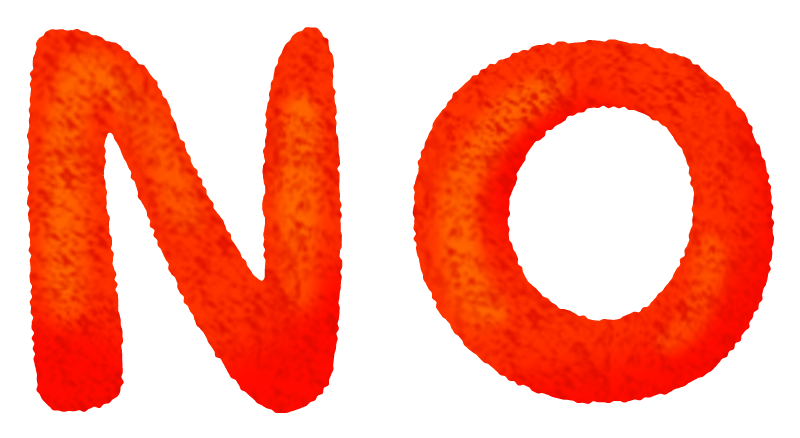
かといって積極的に
辞めるように仕向けるわけでもありません。
私が実際の現場で意識していたのは、
部下が辞めるときは仕方ない
でも私から学んだことが、どこの職場でも
活かせるように成長してほしい。
そして「あなたの部下でよかった」
と思って去ってほしい。
私が実際に営業の現場で
新入社員を教育して得た経験と、
別の現場で間近で見た失敗例。
そして参考にした書籍からの情報を
私なりにかみ砕いて
わかりやすくまとめましたので
ぜひ最後までご覧ください。
参考書籍
今回参考にした本はこの2冊です。
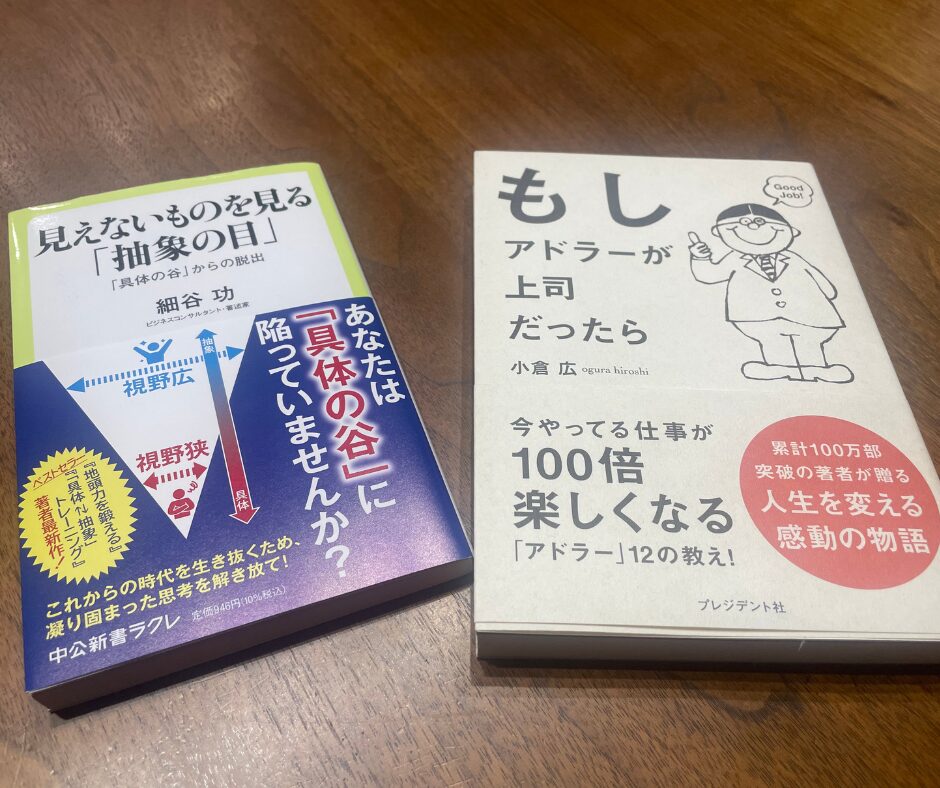
・もしアドラーが上司だったら 小倉広著
アドラー心理学と言えば
「嫌われる勇気」が有名です。
嫌われる勇気は、古代を舞台に
哲学者と青年の対話でアドラー心理学を学びます。
それに対してこの本は現代の会社を舞台に
上司と部下の対話の中でアドラー心理学を学びます。
非常にわかりやすくアドラー心理学を
解説してくれているので
職場の人間関係に悩む人には
間違いなくおススメです。
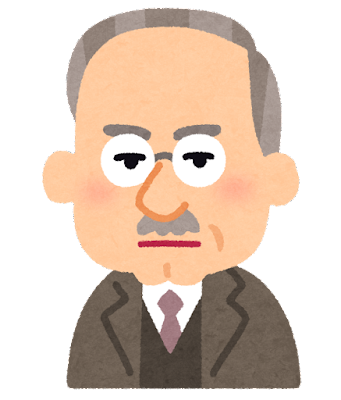
・見えないものを見る「抽象の目」 細谷功著
一般的に、詳細な情報で良い
とされる「具体」を疑い、
ざっくりしていてよくわからない
とされる「抽象」の価値を
考えさせてくれる。
具体的な思考に潜む危険な罠を
「具体の谷」と表現し、
抽象的な思考ができることの重要性を説く。
そして、抽象と具体を上手に往復することが
情報にあふれた現代社会を
生き抜く術であることを
教えてくれる本です。
失敗例
まず失敗例からお話しします。
放置する
私が間近で見た例としては、
教育担当の上司が忙しすぎて
新入社員の不安・不満に
向き合えていないことが挙げられます。
具体的には、
「この資料まとめといて」
と、指示は出すものの、
新入社員からすると当然
やり方がわからない。
質問しようにも上司は
忙しいオーラが出ていて
質問ができない。
勇気を出して質問しても
「まずは自分で考えてから」
とか言われてしまう。
これでは部下は離れていってしまいます。
人ひとりを教育する以上、
自分の業務を犠牲にする覚悟は必要でしょう。
責任を与えない
二つ目の失敗例は
部下に責任を与えないことです。
こんなことがありました。
会議で、発言をするために
教育担当の上司と打ち合わせをして
いざ勇気を出して会議で発言をした。
しかし緊張して打ち合わせ通りにいかず、
何を言いたいのかわからない。
そんな時、部下が発言したい内容を知っている
上司が代わりに話し始める。
新入社員からするとそれは、
カラオケで自分で入れた曲なのに
上司にマイクを奪われた状態
だと言えます。
普通に嫌われます。

↑クソ上司
一度部下に任せると決めた以上
どんな結果になっても
最後まで任せる度胸が
上司には必要です。
もちろん失敗したら取り返しが
つかないことまで新入社員に
任せるという意味ではなく
比較的軽めの責任から
徐々に任せていくという意味です。
最終の責任は当然上司が取りますし、
会社員である以上
全責任は社長にあるのが前提です。
私の経験① 共同体感覚
私が教育担当として意識していたことは
部下が将来退職しても、
次の職場で活躍できる人間に育てる
です。
商品の売り方だけを伝えても
もしこの部下が異業種に転職したら
覚えたノウハウは役に立たない。
自分が、顧客や会社から
求められる役割は何なのか?
を自分の頭で考え、理解し、行動できる
人間に育ってほしい。
それを常に言葉にして伝えていました。
その理念を抱きながら接していたため、
「この顧客をどう契約させるか?」
ではなく
「この顧客の課題をいかに解決するか?」
にフォーカスして向き合うことができました。
アドラー心理学では個の利益より
全体の利益を優先することを
共同体感覚と呼んでいます。
会社の利益より、会社と顧客と社会全体
さらにアドラーは
「永遠の視点から見るように」
との言葉を遺しています。
社会全体の利益を考えるのはもちろん
将来の影響まで考える。
これが実践できた結果、人材育成が
成功したと今なら胸を張って言えます。
共同体感覚を学べるアドラー心理学の本👇
私の経験② 具体と抽象の往復
私は常に
「抽象概念である目的」と「具体的な手段」
を分けて伝えていました。
「この仕事の目的は○○だからね」
と、まず目的を伝え、
「目的を達成する手段は任せるけど、
私はいつもこのように進めているよ。
参考にしてもいいし、自分で考えてもいい」
こんな具合です。
ここでいう目的とは「抽象概念」です。
それに相対するのが「具体的な行動」です。
例えば、「掃除機をかけておいて」
という具体的な指示があるとします。
その目的が「来客があるから」だとします。
目的と具体的な指示をセットで伝えれば
納得感を持って仕事に
取り組むことができるはずです。
このように最初は手間がかかりますが、
徐々に具体と抽象の往復に慣れさせます。
抽象と具体を上手に往復できる人間になれば、
「来客がある」という目的だけで
「掃除機をかける」+「水拭き」
さらに「茶菓子の用意」
まで気を利かせられるかもしれません。
このように徐々に成長していけばいいのです。
もし私が、「来客があるからよろしく」と
目的(抽象概念)だけ伝えたら
部下は何をしていいかわからず
行動できなかったことでしょう。
もし私が、「掃除機をかけておいて」と
具体的な指示だけしていたら
行動はできたとしても
目的不明で成長はなかったでしょう。
私は具体的であればあるほど
良いことだと思っていました。
そんな固定観念を崩してくれたのがこの本です👇
私の経験③ 答え合わせ
参考書籍にはありませんが、
私は自分で考え、答え合わせをする
習慣を大切にしています。

新入社員にも常に
「まずは自分で考えたり、調べる癖をつけなさい」
と言い続けていました。
最初から答えを見て問題集を答えで埋めるより
自分で解いてみてから模範解答を見て
どこで間違えたのかを分析して学ぶ。
この姿勢を教えていました。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
一言でまとめると
「あなたのことをちゃんと見てますよ」
という姿勢が一番大切かもしれません。
この記事は2024年5月に書いています。
この記事が新米上司の方の目にとまり、
人材育成をより良く改善する
きっかけになればうれしいです。
今回参考にした書籍はこちらから
購入可能です。
気になる方は是非ご検討ください。
最後までお読みいただき
ありがとうございます。
私ふじやまは
家族のために頑張る新米パパが
ストレスなく、楽に生きられる様に
なってほしい。
そんな思いで
当ブログ、X(旧Twitter)、
「人生の難易度を下げるために役立つ情報」
を発信しています。
あなたの人生の難易度を下げるのに
お役に立てれば幸いです。
お仕事の依頼は
当ブログの問い合わせフォーム、
または公式LINEからお願いします。
ではまた次回のブログ、X、インスタグラム、
公式LINEでお会いしましょう!
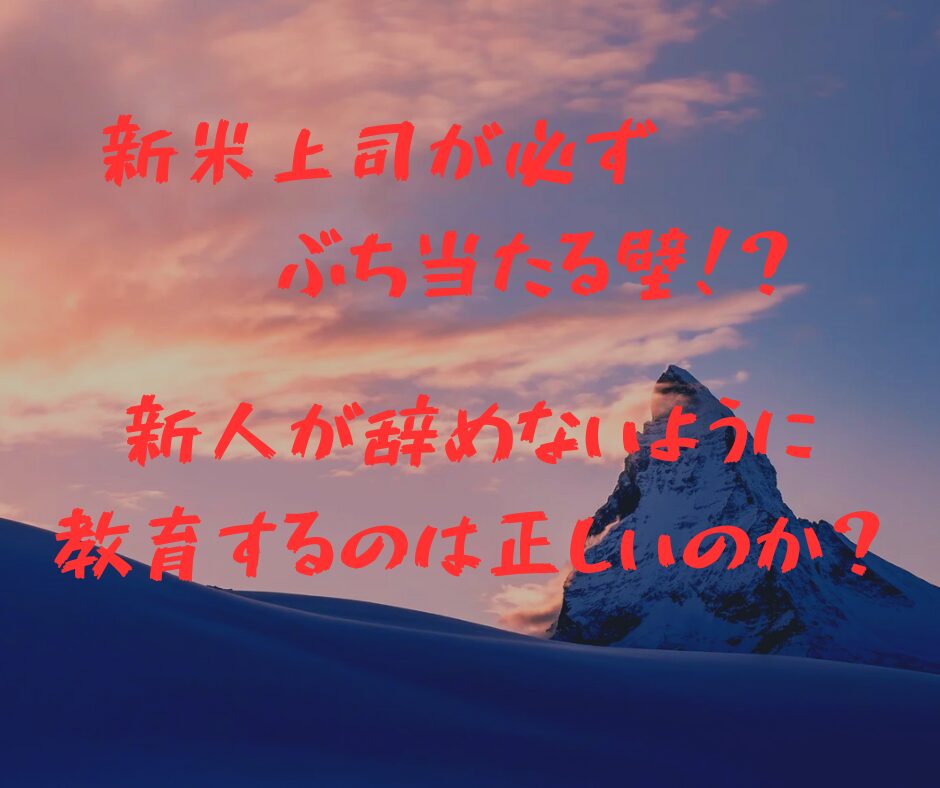


コメント