レーズンやプルーン
乾燥させているとはいっても
水分はたっぷり残っている。
干し芋や干し柿もそう。
ジャムやハチミツは糖分がたくさん
入ってはいるが水分もたっぷり。
なぜ腐ったり劣化したりしないのだろう?
今回の記事ではその疑問を解決します。
料理を科学的に学びたい人
食品の劣化のメカニズムを知りたい人
ぜひ最後まで読んでください。
水分活性
食品中の水分は大きく分けて
「自由水」と「結合水」に分けられます。
水分活性とは、食品中の自由水の割合を示す値のことです。
水分活性の値は0~1の間で示され、
水分のない食品は0、純水が1となります。
自由水
食品成分と結合しておらず、
微生物が利用できる水です。
微生物の増殖、酵素反応、脂質の酸化など、
食品の品質変化に大きく関与します。
結合水
食品の成分(タンパク質、炭水化物など)と
強く結合しており、微生物が利用できない水です。
水分活性の重要性
水分活性は食品の保存性を
考える上で非常に重要です。
微生物は自由水を利用して増殖します。
水分活性が高い(自由水が多く結合水が少ない)
環境ほど微生物は増殖しやすく
食品は腐敗しやすくなります。
逆に水分活性が低い(自由水が少なく結合水が多い)
ほど微生物の増殖は抑えられ
保存性は向上します。
以下の表は食品ごとの水分活性の目安です。
数字が大きい(1に近い)ほど自由水が多く
微生物が増殖しやすいことを示します。

水分活性の制御方法
食品の保存性を高めるために
水分活性を低下させる方法はいくつかあります。
乾燥
食品中の水分を除去することで
水分活性を低下させます
(干しアワビ、干しシイタケ、粉乳など)
冷蔵・冷凍技術、添加物が存在しなかった時代、
保存性を高めるのに最も有効な方法が乾燥です。
その中で、食に貪欲な先人たちは
乾燥材料の「味や食感の変化」を発見します。
技術が発達した現代でも
乾燥材料が取引されるのは
保存性よりも味や食感が好まれるから
という側面が大きいと思われます。
塩漬け・砂糖漬け
塩や砂糖などを食品に加えることで、
自由水と結合させ、
微生物が利用できない結合水の割合を増やします。
(ジャム、梅干し、塩辛など)
ただし減塩が好まれる現代において、
食品メーカーも食味を維持しつつ
塩分の使用を抑える努力をしているので
「塩蔵品なら長期保存できる」と
思い込むのは危険です。
上記のリンクのように
昔ながらの製法で作られた梅干しは塩分18%
減塩で作られた梅干しは塩分僅か3%しかありません。
塩分濃度3%では微生物の繁殖を
抑えるのには全く足りません。
きちんと冷蔵保存した上で、
期限内に食べきることが大前提です。
よく切れる包丁を使う
よく切れる包丁で切ったネギは
パラパラと扱いやすく、
切れない包丁で切ったネギは
水分が出てべちゃっとしている。
そんな経験はないでしょうか?
これは包丁がネギの細胞をつぶして、
本来結合水だった水分を押し出して
自由水にしてしまっているのです。
当然微生物が繁殖しやすく
保存性も悪くなります。
食材はよく切れる包丁で切りましょう。
まとめ
食品の水分と劣化の関係性は
料理や食品の扱いに慣れた人は
感覚的に理解している場合が多いと思います。
それを今回、科学的に解析しました。
調理技術と理論は車の両輪のようなものです。
片方だけでは前進できません。
両方伸ばして前に進みましょう。
私しのらぼは
「料理は科学」「営業は心理学」
をコンセプトに発信しています。
も覗いてみてください。


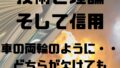
コメント