私は献血に頻繁に行きます。日々忙しく過ごしている中で、何もせずにボーっとしている時間を確保しつつ、社会貢献につながることがとても有益と感じるからです。
そんな献血ですが、敬遠している方も多いと思います。この記事では献血のメリットと注意点をまとめますので最後まで読んでいただけると幸いです。
この記事はこんな方におすすめ
・献血がしたい
・社会貢献がしたい
・AB型
献血の意義
献血とは、けがや病気の治療のために血液が必要な患者さんに健康な血液を提供することを目的として自身の血液を採取・提供することです。
輸血に必要な血液は長期保存することができず、人工的に作ることもできません。そのため私たちは一時期に偏ることなく献血に協力する必要があります。
献血はけがや病気で困っている方のために自分の命を「おすそわけ」するイメージでしょうか。
献血には血液をそのまま採取する全血と、必要な成分のみを分離させてその他は体に戻す成分献血があります。採血している時間は全血で10分から15分程度、成分献血で40分から50分程度です。
なぜ献血に行くのか?その理由は人それぞれかと思いますが、私の場合は大きく分けてふたつ理由があります。
・ひとつはやはり感謝していただけるということがうれしいから
私の血液型はAB型です。比較的少ない血液型なので献血に行くと喜ばれます。それが何となく嬉しくて行き続けています。
・もうひとつは冒頭にも書いたとおり何も考えずボーっとする時間ができるからというもの。
仕事と子育て、日々忙しい中何も考えずにボーっとする時間はなかなか無いもの。献血に行くと強制的に何もしない時間が生まれるので何もしない時間を作るために献血に行き続けています。
アプリの活用
日本赤十字社が「ラブラッド」というアプリを出しています。
アプリでできること
・献血ルームの検索
・献血の予約
・献血可能日の確認
・事前の問診の回答
などです。
特に4つ目の問診の回答は、受付をスムーズに済ませるために有効です。積極的に活用しましょう
献血の流れ

献血の流れは以下の通りです。
①受付 → ②問診 → ③検査 → ④採血 → ⑤休憩
①受付
献血ルームに到着すると受付で献血カードまたはアプリを提示します。体温測定・体重測定といくつかの質問に回答する必要があります。質問への回答はタブレットを使用することが多いですが、アプリを利用すれば事前に済ませることができるのでスムーズです。
ちなみに質問でどのようなことを聞かれるかというと、直近で「出血を伴う歯科治療の有無」「海外渡航歴の有無」「同性同士での性接触の有無」などです。これは感染症を未然に発見する意味で非常に重要な質問です。輸血を必要とする人に迷惑をかけないように正直に答える必要があります。
献血ルームのタブレットで回答しても問題ないですが、事前にあうりで済ませることも可能です。受付スタッフのてを煩わせないように積極的にアプリを活用しましょう
②問診
次は医師による問診へと進みます。
前述の質問への回答に基づいて、献血しても問題ないかどうかを医師が判断します。場合によっては質問を深掘りされたり、新たに質問されたりします。
私の場合、献血に通い始めた当初は念入りに問診されていましたが、最近は献血していても全く問題が起きないので医師の問診は一瞬で終わります(笑)
③検査
血液を少量採取してヘモグロビン濃度の測定を行います。成分献血の場合は血小板の測定も行います。
ここでの採血の方法は2通りあります。
・成分献血の場合は健康診断のように注射を使用して採血する
・全血の場合は指先に針を刺してごく少量の血液を採取する
④献血
いよいよ献血です。リクライニングチェアに座り、リラックスした状態で行います。
血管に針を刺して血液を採取していきますが、献血に使用する針は健康診断や予防接種などで使用する注射針よりも太いです。その影響か、針を刺す際の痛みも少しだけ強いように感じます。我慢できないような痛みや、指先のしびれがある場合は我慢せずに担当の看護師に伝えるようにしましょう。
採血中は読書をしたり動画を見たりして過ごします。
多くの献血ルームでタブレット端末が用意されているので利用してテレビやYouTubeを視聴することができます。採血している腕は動かせないので不便ですが、読書をしてもいいでしょう。
飲み物を飲みながら採血しても構いません。特に成分献血の場合は時時間が長いので好きな飲み物を飲みながらリラックスして過ごします。
採血が終わると針を抜いて4~5分休憩してからチェアからゆっくり立ち上がります。立ち眩みなどがないように手すりなどにつかまりながら立ち上がりましょう。
⑤休憩
血液を大量に抜いているため、水分補給と休憩が必要です。
献血ルームではカップのドリンクの自販機が無料で提供されています。献血を始める前から利用できますし、終わった後の休憩でも好きなドリンクを飲みながら休憩することができます。
また、お菓子をもらうこともできます。専用のコインを使用して自販機でひとつだけ選ぶ場合もあれば、テーブルにフリーで置いてあり好きなだけもらうことができる場合もあり、献血ルームによって異なります。私の経験上、都心部は前者、地方は後者のイメージです。
献血後の休憩は30分程度とることが望ましいとされていますので時間に余裕をもっていくようにしましょう。
献血のメリットと注意点
献血には様々なメリットがあります。
・社会貢献
献血とは自分の命を他人におすそ分けする行為です。これを無償で行うことはとても尊いです。
・血液の健康状態がわかり、健康への意識が向上する
献血が終わると血液の健康状態がアプリに届きます。また、献血に定期的に行くことを習慣にすることで健康に対する意識が高まります。ただしHIVの検査を目的に献血に参加することは禁止されています。
・記念品やお菓子がもらえる
これを目的にしている人は少ないと思いますが、献血に協力するとポイントが付与されて、たまったポイントに応じて記念品と交換することが可能です。また献血ルームではお菓子や飲み物をもらうことができます。
一方注意点もあります。
・献血できない身体状態
献血に協力できない身体状態があります。海外から帰国して間もない場合や、直近で出血を伴う歯科治療を行った場合、ピアスを空けたり刺青をいれてすぐなど血液中に感染症のリスクがある場合が該当します。また、予防接種を受けて間もない場合や薬を服用している場合も該当する可能性があります。受付での質問事項で聞かれる項目に正直に回答すれば誤って血液を提供してしまうことはありませんが、せっかく献血ルームに足を運んでも無駄足になってしまうことになります。事前に調べてから予定を立てることをお勧めします。
・献血の副作用
献血の注射針を刺すのは看護師さんです。当然技術は人それぞれで、自身の血管の状態によっても難易度は変わると思います。強い痛みや痺れが出る可能性もあります。私も過去、成分献血に協力している際に血液が逆流して強い痛みが出たことがあります。担当看護師からは謝罪していただきましたが、しばらく献血は控えようと思うには十分な出来事でした。このような事態が起こる可能性はゼロではないということは頭に入れておくべきでしょう。
・献血に協力した後
献血後は血圧が低下している状態です。気分が悪くなったり、意識を失う可能性があります。血液の成分が回復するにはある程度時間がかかりますが、単純に「量」の回復であれば水分補給によってすぐに可能です。献血後は水分補給と十分な休憩を取り、強い運動や飲酒喫煙などは控えましょう。万が一帰宅中に気分が悪くなったらその場に座るなどして頭を低くする体勢を取り、事故を未然に防ぎます。ちなみに私は何度も献血に協力していますが、気分が悪くなったり意識が遠くなったりしたことはありません。そこまで神経質にならずに頭の片隅に置いておくだけで十分かもしれませんね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
献血は自分の体を資本として社会貢献できる素晴らしい活動です。
ただ、献血に参加する方は若い方を中心に年々右肩下がりに減少しています。
この記事が献血の普及の一助になればこの上なくうれしく思います。
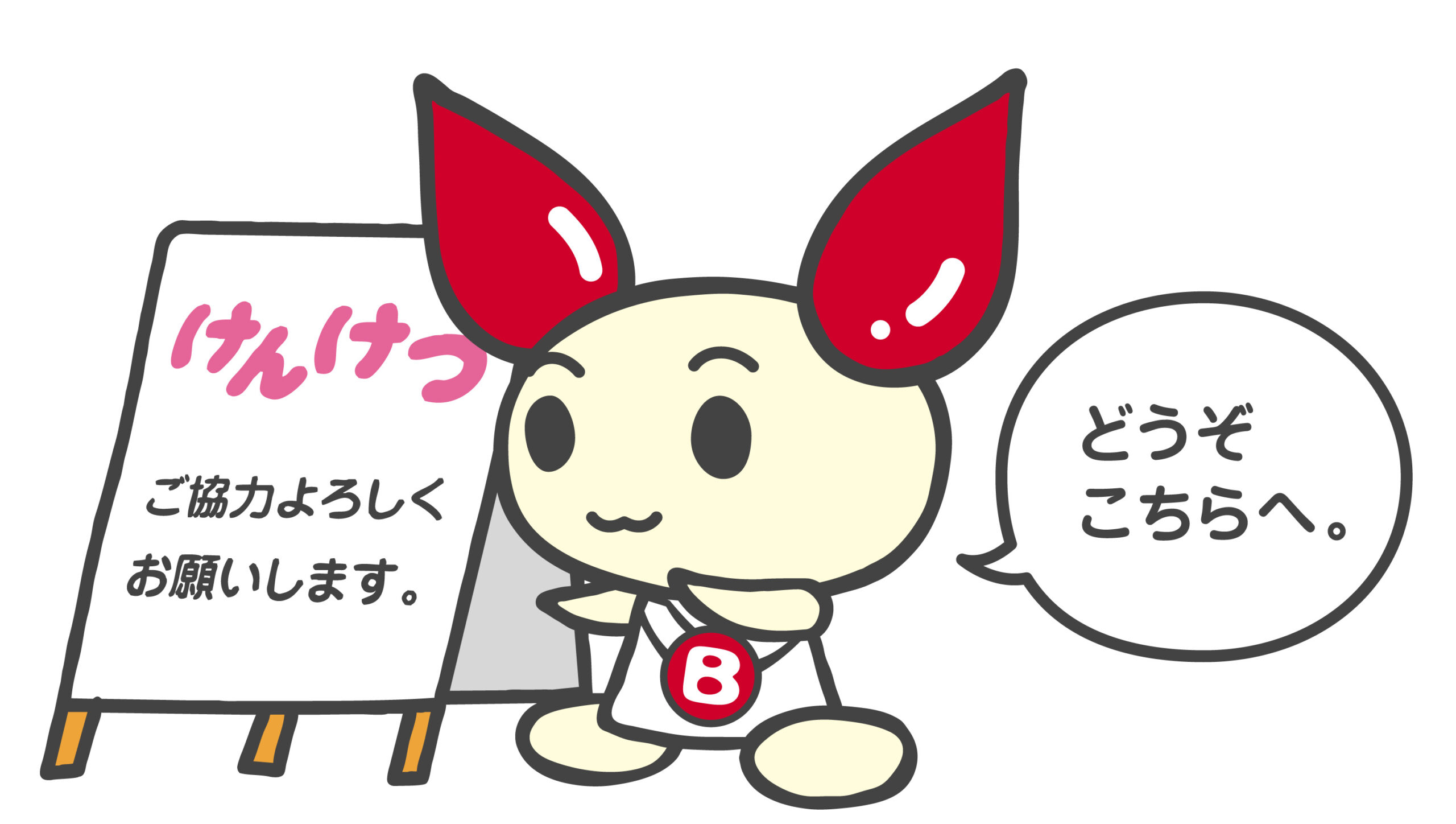




コメント